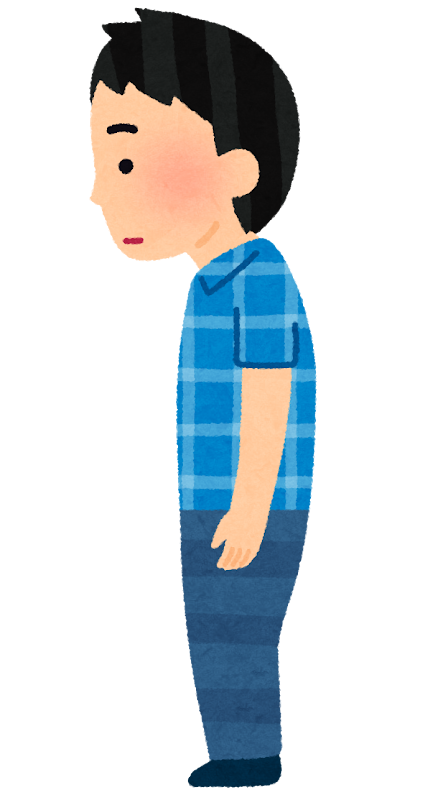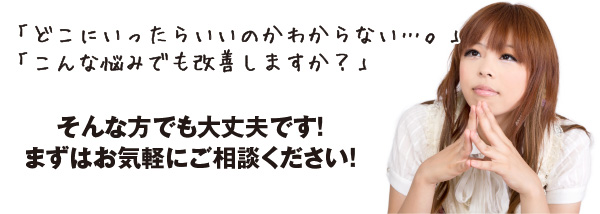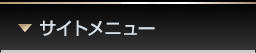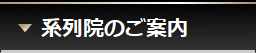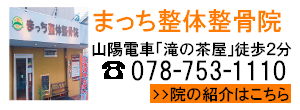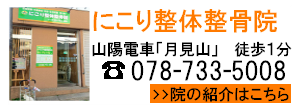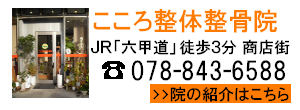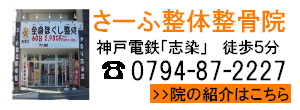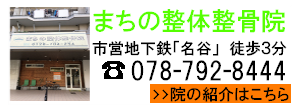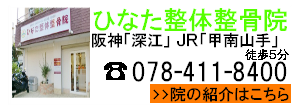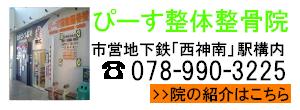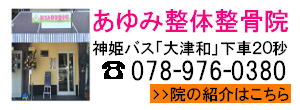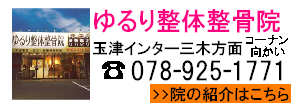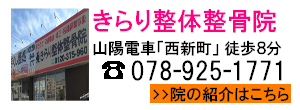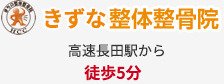自律神経の乱れに注意
2024.04.20
こんにちは(^^♪
すっかり暖かくなり、過ごしやすい季節になりましたが、
春は自律神経の乱れに注意です💦
なぜ春に多い??
春は季節の変化や新生活が始まったりと、
生活の変化などの多い時期です。
そういった中での寒暖差やストレスが原因で乱れることがあります。
自律神経が乱れると、
・身体がだるい
・めまい
・不眠
・頭痛、肩こり
・イライラ、不安
など心身共に様々な不調があります。

普段の生活で、規則正しい就寝・起床や適度な運動、
お風呂にゆっくり浸かる、タンパク質をしっかり摂るなどを心掛けましょう(^^)/
整体でお身体を整えること、鍼灸治療でツボを刺激することも有効すので
ちょっとしたお身体の不調でもお気軽にご相談くださいね♪
当院へのアクセスはこちらをご参照ください。
住所〒653-0812
兵庫県神戸市長田区長田町1-3-1-123 サンドール長田南館1F
診療時間 月・火・水・金・日9:00〜12:00,14:00〜19:00、土 9:00〜14:00
(祝日は通常営業)木曜定休日
MAP
きずなエキテンはこちら⇒
きずなフェィスブックはこちら⇒
きずなLINE@はこちら⇒
きずな事故サイトはこちら⇒
「ツボ」治療☆
2024.04.13
ツボ治療の歴史は古く、鍼灸の知識は6世紀頃に朝鮮半島から日本に伝えられたといわれていて、
平安時代までは灸治療が中心で鍼は外科的な処置を行う際に用いられていたようです✨
平安時代の貴族の日記には灸治療のことがしばしば書かれていて、
戦国時代の武将たちもお灸をすえて戦に赴いた記述があります👊
また有名な『徒然草』や『奥の細 道』でも養生の一環として足の三里のお灸が紹介されています。
この頃はお灸の治療が盛んだったのですが、室町時代後期になると、鍼が盛んになり、
特にツボ(経穴)と経脈に関する研究がたくさん行われて、江戸初期には経穴に関する
学術的な研究書が数多く書かれています📚
日本鍼灸の特徴である管鍼法(鍼を管に挿入した状態で刺入する方法)が編み出されたのも
この時期で、この方法は、初心者でも痛みを与えずに刺入しやすく、 現在でも広く用いられています。
ツボとは?

私たちの体に無数に存在するというツボは、東洋医学では「経穴(けいけつ)」と呼ばれ、
五臓(肝・心・脾・肺・腎)六腑(胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦)の異常「気・血・津液」が
滞るところとして、鍼、お灸、マッサージを行うための場所と考えられています。
また、「気」と「血」が循環する通り道を「経絡(けいらく)」と言い、経穴はその経路の上にあると考えられています。
経穴を刺激することによって気と血の循環を良くし未病状態の体を正常な状態に戻してくれます。
「病気」という文字を見ればお分かりの通り、「気が病む」ことで病気になってしまうのです。
ツボ治療
ツボ治療には、人間本来の持っている「自然治癒力」を高め、弱っている部分を回復させる効果があります。
その代表的な治療法が鍼灸になります。鍼灸でつぼを刺激することで、気と血の流れを調整、
「自然治癒力」を高めて治すことができます。病気や症状を良くするばかりでなく、
継続することで体質の改善、病気にかかりにくい身体作り、予防医学として注目を浴びています。
当院でも積極的に鍼灸治療を勧めています。そのイメージから、“痛いのでは?”と思われる方が
多いようですが、鍼治療を経験された多くの方が「想像していたより痛くなかった」、
「もっと早く来院すればよかった」と言われます。
鍼は非常に細いものを使用しますので、注射のような痛みはありません。
お灸は基本的に台座のあるお灸を使用しています。跡はつきません。症状により直灸も行います。
効果もすばらしいものがあります。初心者の方でも安心して受けて頂けるようになっています。
当院へのアクセスはこちらをご参照ください。
住所〒653-0812
兵庫県神戸市長田区長田町1-3-1-123 サンドール長田南館1F
診療時間 月・火・水・金・日9:00〜12:00,14:00〜19:00、土 9:00〜14:00
(祝日は通常営業)木曜定休日
MAP
きずなエキテンはこちら⇒
きずなフェィスブックはこちら⇒
きずなLINE@はこちら⇒
きずな事故サイトはこちら⇒
吸玉療法って?
2024.04.06
こんにちは(^^♪
吸い玉(カッピング)治療ってご存じでしょうか?
吸い玉とは、ガラスの球状カップを皮膚に吸着させ刺激を与えることで、
体内の血液を浄化し、血行促進する効果が期待できます。
リンパの流れを促進し、身体に溜まった老廃物を効果的に流してくれる働きがあります。

それによる代謝アップで
・冷え性やむくみの改善
・筋肉の緊張状態の緩和
・肩こりや腰痛の改善 が期待できます。
1~2週間ほど痕が残りますが、定期的に吸い玉を続けていくことで
徐々に代謝がよくなり、跡も薄くなってきますよ♪
当院へのアクセスはこちらをご参照ください。
住所〒653-0812
兵庫県神戸市長田区長田町1-3-1-123 サンドール長田南館1F
診療時間 月・火・水・金・日9:00〜12:00,14:00〜19:00、土 9:00〜14:00
(祝日は通常営業)木曜定休日
MAP
きずなエキテンはこちら⇒
きずなフェィスブックはこちら⇒
きずなLINE@はこちら⇒
きずな事故サイトはこちら⇒
花粉症対策
2024.03.30
こんにちは(^^)/
春は過ごしやすい気候ですが花粉症でつらい季節の方も多いですね。

花粉症は自律神経が過剰に反応することで、
鼻炎や目のかゆみ不快感などを引き起こします。
自律神経とは、交感神経と副交感神経の2つから成っており、
私たちの生命活動を勝手に(自律的に)支えてくれています。
寒暖差に合わせて体温を調節できるのも、食べたものを消化・吸収できるのも
自律神経の働きがあるからなのです。
そのため、自律神経を整えることで症状の改善が期待でき
きずなでは、骨盤矯正や鍼灸治療で自律神経を整えていきます!
同時に花粉症状にきくツボも刺激することでつらい症状を緩和していきます☺
毎年のことだから・・・薬で抑えるから・・・と諦めず、
一度治療してみてはいかがでしょうか✨
ちょっとしたお悩み、痛み、不調でもなんでもお気軽にご相談くださいね(^^♪
当院へのアクセスはこちらをご参照ください。
住所〒653-0812
兵庫県神戸市長田区長田町1-3-1-123 サンドール長田南館1F
診療時間 月・火・水・金・日9:00〜12:00,14:00〜19:00、土 9:00〜14:00
(祝日は通常営業)木曜定休日
MAP
きずなエキテンはこちら⇒
きずなフェィスブックはこちら⇒
きずなLINE@はこちら⇒
きずな事故サイトはこちら⇒
姿勢のタイプ
2024.03.23
こんにちは🎵きずな整体整骨院です。
皆さんご自身の姿勢はいいと思いますか??
気を付けているから大丈夫と思っている人でも、
ひょっとしたら間違った知識でご自身を見ているかもしれませんよ。

1猫背タイプ・・・いわゆる猫背姿勢。デスクワークが多かったり、スマホいじりなどで多くの方がこのタイプの姿勢になっています。顔が前に出ていて。横から見ると、耳が肩のラインよりも前にあります。肩も一緒に丸まっている人も多いので、一見耳と肩が同じラインに見える場合があります。壁にかかとをつけて立つと背中が壁に当たるが、頭が壁に当たらない場合はこのタイプです。
2反り腰タイプ・・・女性に多く見られやすい姿勢です。あまり筋肉を使わずに立っています。腹筋が全くできないという方も、この姿勢に多いです。壁にかかとをつけて立ち、腰のすき間に手を入れてください。手がスカスカと入る人は反り腰タイプです。
3背骨がまっすぐなタイプ・・・背骨はキレイなS字カーブを描いた状態が最も理想的です。背骨がまっすぐになりすぎると、腰が丸まっているのが特徴です。壁にかかとをつけて立った時、腰のすきまに手が全く入らない人はこのタイプです。
4胸さがりタイプ・・・このタイプは、横から見ると、胸(ろっ骨)が後ろにずれている姿勢で、身長も低くなってしまいます。壁にかかとをつけて立ち、背中が壁に当たってもおしりが当たらない場合、このタイプの人です。
あなたに当てはまるタイプはありましたか?
姿勢が悪くなる原因は、日常生活の習慣やクセによるものが多く、
筋肉が固まって動きが同じになってしまう事です。
筋肉は同じ動きになれるとその動きばかりしてしまいますので、
同じ姿勢を取り続けていると、筋肉がその姿勢で固まり、長さ等も変わってしまいます。
自分では中々見つけにくのもなので、気になる方は専門家への受診をお勧めします!!
骨盤矯正・姿勢分析・整体・鍼灸治療 ・交通事故など他にも色々・・・
症状に合った治療で皆さまの元気な毎日を全力でサポートします
当院へのアクセスはこちらをご参照ください。
住所〒653-0812
兵庫県神戸市長田区長田町1-3-1-123 サンドール長田南館1F
診療時間 月・火・水・金・日9:00〜12:00,14:00〜19:00、土 9:00〜14:00
(祝日は通常営業)木曜定休日
MAP
きずなエキテンはこちら⇒
きずなフェィスブックはこちら⇒
きずなLINE@はこちら⇒
きずな事故サイトはこちら⇒
ネバネバ食品パワー
2024.03.09
こんにちは きずな整体整骨院です
きずな整体整骨院です
皆さま体調管理はされていますか
インフルエンザなどの感染症予防には、予防注射や、手洗い・うがい、マスクなど
いろいろと対策がありますが、食品に含まれる栄養成分、
特に「ネバネバ食品」が風邪やインフルエンザ予防に役立つと考えられ、研究されているそうです
私たちの身近にあるネバネバ食品とは、オクラ・長いも・山芋・めかぶ・納豆・など
粘りや糸をひくような物質を含む食品です。

ネバネバは、植物が自分の身を守るために、種を守ったり、膜を作って水分をキープしています
こうしたネバネバ成分は人の体内の粘膜にも含まれていて、
気管や消化管、目などの表面をカバーしてくれるのです
植物も、ヒトも守っくれるんです
腸内環境を整えることにも役立ちます。
免疫細胞が集まっていると腸内環境が整い免疫機能もきちんと働くことで、
風邪や感染症にかかりにくくする働きをしてくれます
最近発見されたものでは、めかぶに含まれるフコイダンが
風邪ウイルスの感染を抑制することに有効であるという報告があります
この季節、ネバネバ食品を上手に摂りながら、バランスのよい食生活と規則正しい生活で
風邪や感染症に負けないからだ作りをしてみてはいかがでしょうか
また、鍼灸治療での免疫力アップもおすすめです。
体質を改善し強い身体作りのお手伝いをします!!
骨盤矯正・姿勢分析・整体・鍼灸治療 ・交通事故など他にも色々・・・
症状に合った治療で皆さまの元気な毎日を全力でサポートします
—————————————————
「内なる!パワー!活力アップ!」
—————————————————
\ バランス整え自己治癒力アップ! /
周りの同世代より健康なカラダへ
お身体の悩み・不調等もお気軽にご相談してくださいね
当院へのアクセスはこちらをご参照ください。
住所〒653-0812
兵庫県神戸市長田区長田町1-3-1-123 サンドール長田南館1F
診療時間 月・火・水・金・日9:00〜12:00,14:00〜19:00、土 9:00〜14:00
(祝日は通常営業)木曜定休日
MAP
きずなエキテンはこちら⇒
きずなフェィスブックはこちら⇒
きずなLINE@はこちら⇒
きずな事故サイトはこちら⇒
季節の変わり目の不調でお困りの方へ
2024.02.24
季節の変わり目のこの時期、急な温度変化で身体にかかる負担は日々変化しております。
気候・気温などの外部環境に対応して人間の身体も変化し対応しようとします。
季節の変わり目では気圧が上がったり下がったりすることが多々あり、
気圧が乱高下すると、耳の奥にある三半規管や前庭といった器官に狂いが生じます。
三半規管は体の位置や動きを検知し、前庭は重力や加速度を感じる大事な器官で、
三半規管や前庭の働きに狂いが生じると、脳に間違った情報が伝わります。
しかし、三半規管や前庭以外の器官は脳に正しい情報を伝えるので脳は混乱し、
これが自律神経のストレス反応へとつながってしまいます。
自律神経のストレス反応にはいくつか種類があるのですが、そのうちの1つである交感神経の興奮が続くと、
心拍数の増加、血圧の上昇、慢性痛の悪化、抑うつ、めまいといった異変が起きます。
これが季節の変わり目の不調につながると考えられています。
気候が変動したら(季節が変わったら)、人もそれに合わせて変わっていかなければなりません。
変化への適応がうまくいかないと健康を崩しやすくなります。
健康管理のため運動・食事・睡眠など日常生活で気をつけたいこともありますが、
この時期の体調管理には血液の流れがとても大切になってます。
人間の体は寒くなればその寒さに慣れてきますし、暑くても同じになります。
気温差が激しいと、体は付いてくるのに必死な状態が続きます。
季節の変わり目の不調は、季節や気候の急激な変化に体を慣らせようとして起きます。
そして自律神経が変化に対応できないときにつらい症状を起こしているので、
放置することなく対策を講じていきましょう。目標は変化に耐えられる体をつくることです。
日々の入浴やカイロ等で患部を温めることで血行促進につながり、冷えによる関節・筋肉の緊張を軽減できます。
その他、水で絞ったタオルを電子レンジで温めて、気になる所・患部に当てることもおススメです。
また、食べ物で身体を温めると内臓など体の内側から温まり血行をよくすることができます。
季節の変わり目の不調を起こしている人が朝食を摂っていない場合、朝食を食べることをおすすめします。
体温は眠っている間に下がっていくのですが、朝食を摂ることで一気に正常に戻ります。
体温を正常に保つことは自律神経の働きを整えることにつながります。
季節の変わり目の不調は脳の軽い不調で起きている可能性があるので、脳に栄養を行き渡らせることが対策に
なることがあります。
ビタミンB1は、細胞が糖をエネルギーに変えるときに必要となる物質です。
そのためビタミンB1をしっかり摂取していると、脳細胞が糖を吸収して活性化します。
ビタミンB1を多く含む食材は、豚肉、ウナギ、カツオ節、真鯛、紅鮭、大豆、小豆、玄米、などです。
また、神経と免疫は深い関係にあり、神経は免疫を制御しています。
また、免疫が弱体化すると神経が異常をきたすこともわかっています。
そのため、適度な運動習慣を身につけたり、ストレスを溜めないようにしたり、腸内環境を整えたり、
笑ったりして免疫を高めれば、自律神経を守ることにつながります。
自律神経が守られれば、季節の変わり目の不調の軽減が期待できます。
季節が変わるときに体調が悪化するのは「気のせい」などではありません。
体調管理に気をつけて、対策を講じることで、季節に煩わされることなく働くことができるでしょう。